組織変革の『ディスラプティブ・ランゲージ』を探求する – ニューロリーダーシップ・サミット参加から得られた洞察 –

「Disruption(ディスラプション)」。崩壊、混乱、破壊といった意味合いをもつこの言葉は、既存の枠組み、体制、技術、ビジネスのあり方が一変し、新たなイノベーションが生まれる現代を象徴するものとして、ビジネスの世界を席巻しています。日本においても、たとえば昨年秋に、IMDのマイケル・ウェイド教授らによる『対デジタル・ディスラプター戦略 既存企業の戦い方(日本経済新聞社)』といった、邦題のタイトルにディスラプションが付く書籍が発刊されたり、ネット上でもキーワードとして目にする機会が増えてきています。特にこの1~2年は、「ディスラプティブな時代に企業がどう向き合うのか」といった問いが、企業経営に携わる人々に突き付けられた年でもあり、今後もそうした傾向は強まると思われます。 では、そうしたディスラプティブな時代において、人や組織に携わるHRは何を考えていくべきでしょうか。私たちが昨年秋に参加した「ニューロリーダーシップ・サミット2017」は、まさに「Thrive through Disruption(ディスラプティブな時代に成長する)」というテーマを主題に掲げ、グローバル企業で働くHRの実践家、経営者、コンサルタント、そして脳科学者が、領域の垣根を超えて多様な議論を行い、挑もうとしたサミットでした。 本サミットに、ヒューマンバリューから2名(川口、松山)が参加しました。本レポートでは、2日間のサミットで語られたテーマや議論の内容、そして得られた洞察を幅広く紹介し、ディスラプティブな時代に私たちが貢献できることは何かを考えるきっかけとしていきたいと思います。
ディスラプティブな時代には、ディスラプティブな言語が必要
ニューロリーダーシップ・サミットは、デイビッド・ロック氏がCEOを務めるニューロリーダーシップ・インスティチュート(以下、NLI)が主催するサミットとして2007年から毎年開催されています。名前にもある通り、ニューロサイエンス(脳科学)をベースに、既存のリーダーシップやマネジメントのあり方を再考していくことに主眼が置かれています。11回目を迎える2017年のサミットには、32カ国341の組織から628名が参加しました。参加企業もアマゾンやマイクロソフト、グーグルのようなデジタル系の企業から、ギャップ、コカ・コーラ、ゴールドマン・サックスなど様々です。また、ニューヨーク大学やコロンビア大学、UCLAなどで脳科学を研究する若手の研究者たちが多く参加し、登壇しているのも本サミットの特徴といえるでしょう。

サミットでは、毎年大きなテーマが設けられていますが、今年は上述した「Thrive through Disruption(ディスラプティブな時代に成長する)」がメインテーマです。オープニング・セッションでは、デイビッド・ロック氏、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授、ヒューレット・パッカードでCHROを務めるトレーシー・ケオー氏らが登壇しましたが、その中では、「ディスラプティブな時代には、私たちは新たなDisruptive Language(ディスラプティブな言語)を生み出し、根付かせていくことが必要ではないか」という興味深い提言がなされました。
ディスラプティブな時代には、私たちは新たなDisruptive Language(ディスラプティブな言語)を生み出し、根付かせていくことが必要ではないか
デイビッド・ロック氏
「ディスラプティブな言語が必要」とはどういう意味でしょうか。デイビッド・ロック氏は、音楽を比喩に用いて次のように話します。「人は、音楽について何も知らない状態から、『クラシック』や『ジャズ』といった言葉を通して、音楽の見方が変わります。あなたが何もしなくても、こうした言葉が私たちの世界の見方に変革を起こすのです。たとえばヒューレット・パッカードでは、“Imagine the Future“という言語が掲げられていますが、こうした言語が無意識に私たちの行動を価値づけ、方向づけたり(Unconscious Priming)、また意識的に自分たちの行動が正しかったのかを較正(Conscious Calibration)しようとするのです」
少し拡大解釈して考えてみると、たとえば「言葉が世界をつくる」という考え方がありますが、私たちは言葉を介して物事を認知し、考えたり、行動に移し、それが強化されて文化や関係性を築いていきます。サミットで行われた主張は、今私たちがビジネスやマネジメントで使っている言葉が、今のDisruptiveな時代に対応していないのではないかというように受け取れます。たとえば日常の中で、「売上」「利益」「コスト」といった言葉を当たり前に使うのと同じように、イノベーションと変化の時代に即した新たな言葉を生み出し、経営者・マネジャー・メンバー、そしてHRがそうした新たな言葉への理解を深め、使っていけるようにしよう、そして仕事や組織を新たな枠組みで捉え直していこうというのがサミット全体を通して貫かれていたテーマだったように思います。
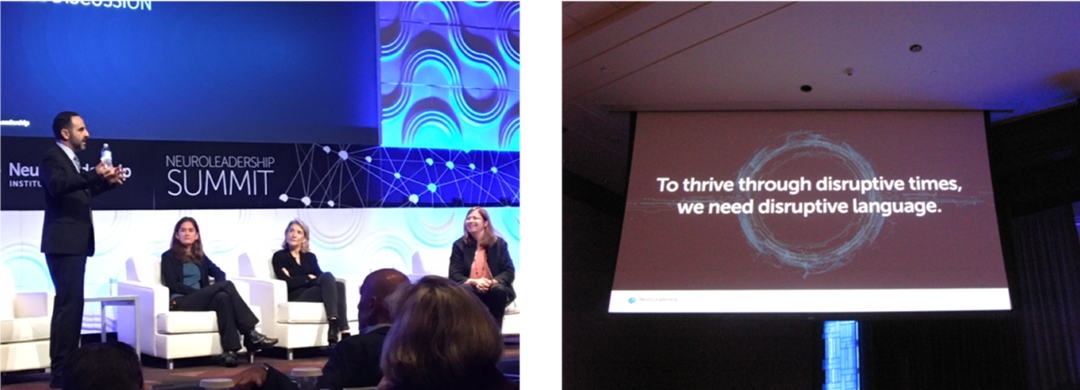 オープニング・セッションでは、ディスラプティブ・ランゲージについての議論が行われた
オープニング・セッションでは、ディスラプティブ・ランゲージについての議論が行われた
それでは、私たちが生み出していきたい、考えていきたい、理解を深めていきたい、「ディスラプティブな言語」にはどのようなものがあるでしょうか。サミットでも明確な定義や正解が示されたわけではなく、まだまだこれから考えていくべきものと思われますが、大きく以下のような「言語」をもとに議論・探求が行われていました。
「ディスラプティブな言語」としての議論テーマ(例)
1. 『グロース・マインドセット』
2. 『パーパス(目的)』
3. 『フィードバック・マネジメント』
4. 『インクルージョン』
5. 『スマートなチーム』
6. 『カルチャーの変革』
その他(エンプロイー・エクスペリエンス、アジャイル・オーガニゼーション…)…etc
以降では、各テーマにおいて実際にどんな議論や検討が行われていたのかを紹介していきたいと思います。
1.『グロース・マインドセット』を育む「認知フレーム」「実験」「相互学習」
ニューロリーダーシップ・サミットは、現在のパフォーマンス・マネジメント革新のトレンドに大きな影響を与えたサミットとして知られていますが、その動向の中で、『グロース・マインドセット』という言語ほど私たちに大きな影響をもたらしたものはないかもしれません。オープニングのキーノートに登壇したハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授は、著書『チームが機能するとはどういうことか』の中で、認知フレームの重要性を述べており、その中で、「仕事を『作業を行う場』としてフレーミングすると、『学習する場』としてフレーミングした場合に比べ、人々はリスクを回避する傾向があり、困難にひるむことなく、最後まで立ち向かおうとしなくなる」というキャロル・ドゥエックらの研究を紹介しています。私たちが「グロース・マインドセット」という言語で仕事を認知するのか、あるいは「フィックスト・マインドセット」という言語で認知するのかによって、働く人々、チーム、組織、事業に大きな違いが生まれていきます。
ニューロリーダーシップ・サミットにおいても、グロース・マインドセットは大きなテーマとして数年前から扱われています。今年は、コロンビア大学のケビン・オシュナー博士、インテル社のメラニー・デイビス氏、ノキア社のマイケル・キシュナー氏、NLIのリサ・ロック氏によるパネル・ディスカッションが行われましたが、グロース・マインドセットの重要性が明確になった今、今年はそれをどう育んでいくかに議論が踏み込んできたように感じました。
たとえば、冒頭で発表を行ったケビン・オシュナー博士は、グロース・マインドセットを育む鍵として「エクスペリメント(実験)」の重要性に着目しています。ここで使われているエクスペリメント(実験)は、決して科学者やエンジニアが研究室の中で行う実験のみを指しているわけではありません。働く一人ひとりが日々の仕事の中で様々な実験やチャレンジを行って、そこから学んでいく行為がグロース・マインドセットを育むという意味合いで使われています。日常的なルーティンや反応的・反射的な行動と異なり、エクスペリメントには、努力、集中力、アウェアネス、創造的な思考、学習、洞察といったものが伴います。しかしながら、私たちの脳は、どちらかというとゴールや結果志向になりがちで、プロセスやプログレスにフォーカスを当てることが苦手でもあります。そこで、オシュナー博士は、「エクスペリメンタルな習慣」をもつことを推奨しています。たとえば、ジャーナルを書いたり、セルフ・モニタリングのツールなどを活用しながら、自分の行動が時間とともにどう変化し、どのように成果にたどり着いたのかということを記録していくことが、学びを促進し、将来の実験を可能にすると述べていました。
そして、ノキアとインテルの2社からは、企業の立場として、どのようにエクスペリメントを促進したり、プログレスを記録しているのかといったことが話されていました。両社とも会社全体としてグロース・マインドセットに取り組むことの意味やバリューを社員に共有し、実現していきたい意識や行動としてフレーミングすることを、まず前提とすることから始めています(ノキアは、会社の戦略、カルチャー・バリュー、そしてリーダーシップ・トレーニングの3つの柱に、グロース・マインドセットの要素を入れ込んでいるとのことでした)。そして、実践の場では、マネジャーとメンバーが(またメンバー間で)、プログレスにフォーカスを当てたカンバセーションを定期的に行うことを重視ししており、メンバーが何を学び、どう成長したのかをリフレクションできるような会話の質を高めていくための教育の場をもったり、互いに学び合うソーシャル・ラーニングの場をもつことに投資している姿勢がうかがえました。
セッションの中では、企業がグロース・マインドセットを育む上では、「会社全体で認知フレームを形成すること」「実験の習慣を育むこと」、そして「相互に学び合う環境を創ること」が、ベースとなるレバレッジ・ポイントとして語られている印象をもちました。今後はこうしたポイントを具体的に実践していくための方法論やティップスの探求が行われていくように思います。
2.『パーパス(目的)』の目的を探求する
グロース・マインドセットに影響を与えるものとして、「パーパス(目的)」という言葉にも注目が集まっています。ディスラプティブな時代だからこそ、企業や個人が、不確実な状況でも揺るがない、高いパーパス(目的)をもつことの意義が、かつてないほど高まっているように思います。NLIのジャッキー・グレイ博士は、「パーパスこそが、雇用者が選ばれ、そこで働き続けることに影響を与える最も大きな要因です」と述べ、その理由として「約50%の人が、刺激的なパーパスをもつ会社で働くためなら、15%の給料のカットを受け入れると答えている」「3分の2の人が、より高いパーパスが、自分の仕事でより一層の努力をするようモチベートすると答えている」といったデータを紹介していました。
そうした背景もあり、今年のサミットでは、パーパスをメインテーマとした、「The Purpose of “Purpose”:『パーパス(目的)』の目的とは?」というセッションが初めて開催されました。セッションには、上述のグレイ博士をはじめ、EQの研究で知られるアニー・マッキー氏、オレゴン大学のエリオット・バークマン博士、そしてジュナイパー社のテレーズ・ケンブル氏が登壇しました。冒頭のスピーチの中で、アニー・マッキー氏は自身の新著「How to be happy at work」を引き合いに出しながら、次のように語りました。「幸せには3つの構成要素があります。パーパス(目的)、ホープ(希望)、そしてフレンドシップ(友情)です。中でも、パーパスは、私たちを動かす源泉となります。なぜ自分は、朝起きて、子どもたちを家庭に置いてでも、職場に行くのか。それは、そこにパーパスがあるからです」。
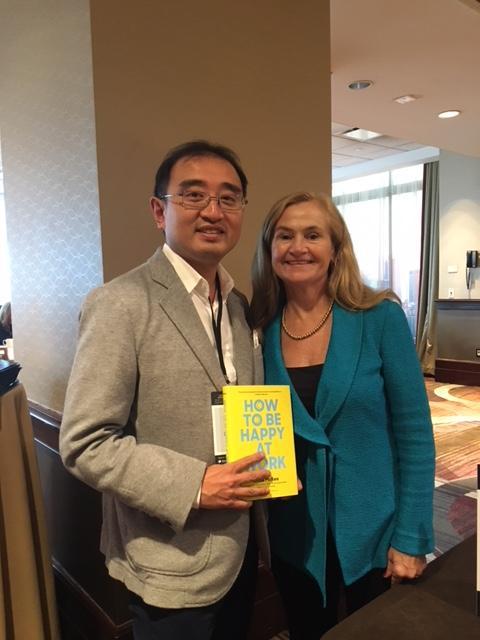 川口とアニー・マッキー氏
川口とアニー・マッキー氏
そして、セッションの中では、バークマン博士が脳科学の視点から、「Why」と「How」の違いに関するプレゼンテーションを行いました。「Why」とは、より高次で抽象的な目的を指し、「How」は、より低次で具体的な手段や行為を指します。たとえば、「エクササイズを行う」といった行為に対して、「なぜそれを行うのか?」「健康になりたいから」「なぜ健康になりたいのか?」という問いを繰り返していくと、究極的には自分自身のアイデンティティ、つまり自己の「パーパス」につながっていきます。バークマン博士は、WhyとHowの両者が重要であることを前提に置きながらも、それぞれを考える脳内のネットワークは異なっていて、トレードオフの関係にあるため、私たちはWhyとHowを同時に考えることはできないという視点を脳のメカニズムを通して解説します。それに加えて、ストレスが高くネガティブで圧倒されるような環境では、人の脳は近視眼的になり、低い次元の思考に向かいやすくなるという研究結果(Gabie & Harmon-Jone、2010)を紹介し、現代においては目的について考えづらくなっていることへの警鐘を鳴らしていました。後に続くパネル・ディスカッションの中では、そうした状況だからこそ、「セルフ・リフレクション」を行う時間を丁寧に確保し、自己のコア・バリューを明らかにすること、またそうした気づき(セルフ・アウエアネス)が起きる場を日常の中でつくっていくことが重要といった指摘がなされていました。
また、バークマン博士は、パーパスを考えることの効用として、「パーパスが人の考え方を柔軟にする」という視点を述べていました。なぜなら、一段高いパーパスを考えることで、一段低い行動の選択肢が広がるからです。ディスラプティブな時代には、目の前で様々な変化が繰り返されます。そうした変化の波の中で、自分がやるべきことが変化したとしても、パーパスに立ち返ることで、そこに柔軟に意味を見出せるようにしていくことが重要といえるかもしれません。この点は、別のセッションにおいても、ペンシルベニア大学のエミリー・フォーク博士が、自身のコア・バリューを探求する機会をもつことができると、変化を受け入れやすくなるという研究を紹介しています。また、エイミー・エドモンドソン教授は、ハーバード・ビジネス・レビュー誌に寄せた論文の中で、「順応性のあるビジョン」を持つことの価値について言及しており、変化の時代においては、ビジョンは進化することが前提であり、その際、自分たちが大切にしている価値観に立ち戻って、新たなビジョンが意味のあるものであることを認識することが重要と主張しています。
バークマン博士らのプレゼンテーションを受けて、セッションでは、「何が良いパーパスを生み出すのか?そこにどう近づけるのか?」といった視点から様々な対話が行われました。たとえば、以下のような発言がパネラーからも投げかけられました。
「パーパスを考える上で、阻害要因になるのが『○○すべき』という外的規範による考え方です。私はこれを『Should Trap(~すべきの罠)』と呼んでいて、私たちは子どものころからこの呪縛にとらわれています。こうした罠から脱却して、私たちはいかに真の目的に迫れるのでしょうか」(アニー・マッキー氏)
「パーパスは企業経営のあらゆるレベルに存在します。組織のビジョンやミッションがあるのと同様に、チームにはチームの目的があり、1つひとつのミーティングにも各ミーティングの目的があり、各自のタスクにも目的があります。すべてのレベルで目的を意識し、レバレッジとして活用していくことが重要です」(ジャッキー・グレイ博士)
「企業にとってのチャレンジは、何千、何万といる社員一人ひとりが、個人のパーパスと会社のミッションをコネクトできるか、そして、それをどのように支援できるのかにあります。企業は会社のミッションを一方的に展開するのではなく、個人のパーパスにもっと耳を傾けるべきです」(テレーズ・ケンブル氏)
昨今、新しい組織のあり方として日本で話題になっているTeal組織においても、組織のあり方を進化させていく原理として目的の重要性が述べられています。今後、パーパスがもつ意味や価値について、脳科学の知見も取り入れながら再考が進んでいくように思います。
 パーパスに関するパネル・ディスカッションでは様々な探求が行われた
パーパスに関するパネル・ディスカッションでは様々な探求が行われた
3.『フィードバック・マネジメント』のフォーカスは「与えること」から「もらうこと」に
グロース・マインドセットを育む上で、「フィードバック」が重要であるということは、共通の認識になってきているように思います。ニューロリーダーシップ・サミットでは、パフォーマンス・マネジメントに関する次代のテーマとして、「フィードバック・マネジメント」を取り上げています。たとえば、GEやマイクロソフトでは、「フィードバック」という言葉自体が、恐れや不安を生み出してしまうので、「インサイト」や「パースペクティブ」と呼ぶなど、新たな言葉を創り出して、フィードバックが効果的に進むような職場づくりを進めようとしています。
そうした背景から、ニューロリーダーシップ・サミットにおいても、フィードバック・マネジメントは特に関心の高いテーマとして、ここ数年多くの人が議論に参加しています。今年は、ニューヨーク大学のテッサ・ウエスト博士、マイクロソフトのリズ・フリードマン氏、ヒューレット・パッカードのマイク・ジョーダン氏、リフレクティブ社CEOのラジーフ・ベヘラ氏、NLIのべス・ジョーンズ氏が登壇し、パネル・ディスカッションが行われました。
NLIは、2016年からフィードバックについて、彼らの調査研究に基づいた1つの主張を行っています。それは、「フィードバックを与えること」にフォーカスするのではなく、「フィードバックをもらうこと」にフォーカスしようというものです。フィードバックを与える側主導で考えると、フィードバックを受ける側に「自分が挑まれている」といった恐れを与えるだけではなく、フィードバックを与える側にも「正しいフィードバックを行わなければならない」といった感覚を与え、困難を伴うことになります。そこで、見方を変えて、フィードバックを受ける側がフィードバックを積極的にもらえるような状況を創り出していくことにフォーカスを移すべきではないかというのが、主張の中味です。NLIのCEOのデイビッド・ロック氏は、次のように述べ、その効果に言及しています。「トップ・パフォーマーほどフィードバックを積極的に求めようとします。フィードバックを求めることにフォーカスすることで、与える人・受ける人の両者が恐れを手放せたり、より素早く定期的にフィードバックが行われたり、バイアスを少なくしてできるだけたくさんの人からフィードバックをもらえるようになります」
 フィードバックを与えるのではなく、もらうことにフォーカスの舵を切ろうというメッセージは、多くの参加者の共感を呼んでいた
フィードバックを与えるのではなく、もらうことにフォーカスの舵を切ろうというメッセージは、多くの参加者の共感を呼んでいた
2017年のサミットでは、こうした主張を検証すべく、ニューヨーク大学のテッサ・ウエスト氏が、NLIとコンサルティング会社のKPMGと協働で行った実験の様子を紹介していました。実験は、KPMGの社員に1対1のネゴシエーションのロールプレイングを行ってもらい、その後、相互にフィードバックを与えたり、求めたりするときの体の反応(心拍数)などを測定するものでした。実験の中では、たとえば、「フィードバックを与える」行為を最初に実施するときは、心拍数が高く、かつポジティブな言葉が増えるようです。そこから、人は求められていないフィードバックを行う際には、“Brittle Smiles(もろいスマイル)”効果(肌の下でのストレス反応を伴いながら、あからさまで、過剰なポジティブさを見せる)による反応があるのではといった仮説が紹介されていました。また、最初にフィードバックを求める行為を取ると、その後の両者の相互作用をスムーズにする潤滑油として働き、ペア同士が良い状態になるといった興味深い仮説も報告されていました。
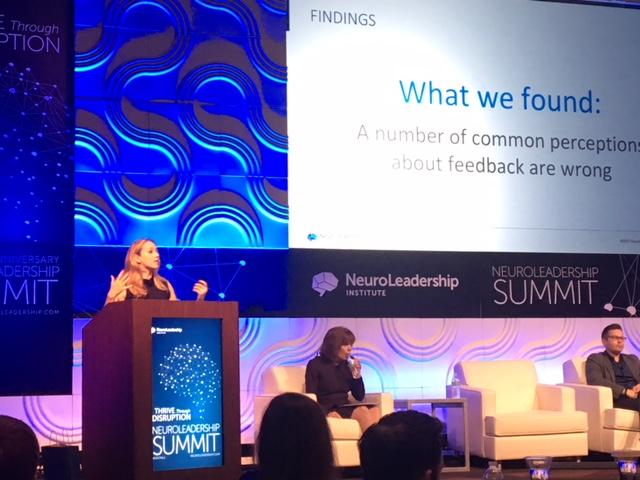 フィードバックに関する実験結果を紹介するニューヨーク大学テッサ・ウエスト博士
フィードバックに関する実験結果を紹介するニューヨーク大学テッサ・ウエスト博士
こうした議論は、ニューロリーダーシップ・サミット以外でも増えているように感じます。少しフィードバックの議論から外れますが、たとえば、世界最大のタレント・ディベロップメントのカンファレンスATD-ICEにおいては、ランディ・エメロ氏が「モダン・メンタリング」というコンセプトを提唱しています。旧来のメンタリングは、人事部のマッチングによって、シニアと若手リーダー層が1対1の関係を常に同じ人と結び、定期的に会って長時間をかけてメンタリングを行うようなスタイルですが、これは今の時代ではうまくいかないとのことです。その背景には、ソーシャル・ネットワークの環境で育ってきたミレニアル世代は、こうした硬直的で一方向的な学びのあり方を好まないことが挙げられています。今日的なメンタリングのあり方として、誰もが学習者であり、誰もがアドバイザーになれるような、メンタリングのネットワークを創り、より多くの人の経験やストーリーから、気軽に、短時間で、時にはバーチャルで、フラットに学び合えるような環境を創っていくことが推奨されていました。この辺りは、上述のフィードバックの議論と通ずるものがあるように思います。
フィードバックをカンパニー・センタードで与える(与えさせる)といった視点を脱却して、ピープル・センタードで、メンバーが積極的にフィードバックをもらいやすいようなマインドセットや職場環境をどうつくっていくかが、今後のポイントになるかもしれないと感じたセッションでした。
4.『インクルージョン』を高める企業のチャレンジ
ニューロリーダーシップ・サミットでは、D&I(ダイバーシティー & インクルージョン)の領域に科学の知見を生かしていくことへの関心も高まっています。過去のサミットでは、主にバイアスを扱うセッションが行われていました。今回のサミットでは、NLIのハイディ・グラント・ハルバーソン博士、UCバークリーのロドルフォ・メンドーサ・デントン博士、BNYメロンのジョティ・チョプラ氏、そしてJPモルガン・チェースでシニア・ダイバーシティー・アドバイザーを務めるパトリシア・デイビッド博士が登壇し、「インクルージョンを高める」をテーマにセッションを行いました。
米国では、数多くの会社がD&I(ダイバーシティ & インクルージョン)に力を入れています。セッションでは、その背景として、ダイバーシティ(多様性)の高い組織は、忍耐力、創造性、業績、すべてにおいてポテンシャルが高いとのデータが紹介されていました。
そして、D&Iの中でも、ダイバーシティを高めることに関しては、米国企業は得意ですが、インクルージョンに関しては、まだ大きな課題があるとの問題提起が行われています。多様性の高いチームの良い特徴を生かすためには、インクルージョン(仲間意識)も高いことが条件になりますが、多様性の高いチームにおいて、インクルージョンは、達成するのも保つのも困難が伴います。似ているもの同士で一緒にいることは自然で居心地が良いのに対して、似ていないもの同士、いわゆる多様性の高いチームのメンバーが一緒にいることは居心地が悪いからです。そのため、多様なメンバー同士でインクルージョンを徹底するのは困難な上に、一度実現できても、継続してインクルージョンを促す努力をしていないと、知らないうちにエクスクルージョン(仲間外れに)されたと感じるメンバーができる可能性が高いとの指摘がなされていました。
今回のセッションでは、脳科学の観点からも、インクルージョンを解題し、理解を深める試みがなされていました。ハイディ・グラント・ハルバーソンからは、「人間の脳は、自分が仲間外れにされたと認識をしたとき、けがをして痛みを感じたときと同じ部分が反応をしている」との研究結果を引用していました。こうした反応が起きるのは、人間は他の動物と比べて身体的には弱く、他人と協力し合って生活をしないと生き延びることが困難であり、仲間外れにされるということは、死と同等の意味をもつということが背景として挙げられていました。
そして、組織のメンバーが自分が仲間外れにされたと感じると、以下の悪影響も見られるとの研究内容を紹介していました。
Exclusionによる悪影響:
1. Reduced intelligent thought and reasoning. (脳の機能が低下する)
2. Increased self-defeating behavior(自爆行動が増える)
3. Reduced pro-social behavior(社会貢献要望が低くなる)
4. Impaired self-regulation(自己管理能力が弱くなる)
5. Reduced meaning and purpose(いる意味や目的が薄れる)
6. Decreased well-being(健康を害する)
研究結果の紹介に加えて、登壇者の個人の経験に基づいたパネル・ディスカッションも、企業内のリアリティが感じられ、興味深かったです。たとえば、JP Morgan Chaseのパトリシア・デイビッド博士は、「私は35年間社員をインタビューしてきましたが、気づけば一度も体が不自由な人とは話したことはありませんでした。意図的ではなかったのですが、気づかないうちに彼らをエクスクルード(仲間外れに)していたのかもしれません」といった自己の体験を語り、共感を呼んでいました。人を仲間外れにしてしまうのは、多くの場合は意図的ではなく、不本意にしてしまうといったことがパネルの中でも強調されていました。
また、パネル・ディスカッションでは、企業が実践しているインクルージョンを高める取り組みの失敗例についても言及がなされていました。
たとえば、米国企業では、会話の中に差別的だと思われる可能性がある発言を入れないようにする「マイクロ・アグレッション」のトレーニングがここ数年行われています。そのトレーニングの中では、「発してはいけない言葉や禁止されている行動」などが100以上載っているリストが渡されたりします。しかし、そうしたリストを意識し過ぎたために言動が不自然になり、結局そのトレーニングによってインクルージョンを高めようとした対象のグループを、よりエクスクルードしてしまうといった副作用が起きるなどの報告もなされていました。また、デロイト社では、「ヒスパニック・グループ」や「女性グループ」といったグループに対するラベル付けがあることで、より違いが強調されてしまうため、生まれもった特徴でグループ分けを行うことを廃止したといったことが紹介されていました。
サミットが行われた米国では、人種や宗教の多様性が目立ちますが、日本では思考の多様性であったり、生活習慣の多様性であったり、目に見えにくいところでダイバーシティが存在するなど、同じダイバーシティでも意味合いや与える影響に違いもあります。そうした状況におけるインクルージョンのチャレンジとは本質的にどんなものか、サミットを起点に私たちも考えていきたいと感じました。
 インクルージョンに関するセッションのパネル・ディスカッションの様子
インクルージョンに関するセッションのパネル・ディスカッションの様子
5.『スマートなチーム』をニューロサイエンスから探求する
ディスラプティブな時代において、かつてないほどチームでのコラボレーションが求められています。そうした背景もあり、今回のサミットでは、個人のキャパシティのテーマを超えて、チームに焦点が当てられていました。本セッションには、UCLAのソーシャル・コグニティブ・ニューロサイエンス・ラボ所長のマット・リーバーマン博士をはじめ、IBMのデブ・バブ氏、NLIのデイビッド・ロック氏、カーリル・スミス氏が登壇し、脳科学の視点を交えてスマートなチームのあり方が探求されました。今回最も注目度の高かったセッションと言えるかもしれません。
冒頭では、デイビッド・ロック氏からチームに関するサーベイのデータが紹介されていましたが、それによると、約90%の組織が複雑な問題解決にチームが不可欠と考えているにもかかわらず、チームの連携に自信をもっている経営者は12%に過ぎないとのことでした。チームの重要性が認識されている一方で、どのように良いチームを構成するのかがわかっていない実態も見えてきます。たとえば、個人として優秀な人物を組み合わせてチームにしても、必ずしも一番良いチームが出来上がるとは限りません。スターと呼ばれているプレイヤーが転職しても、46%の人たちは5年ほど経たないと以前の会社と同じレベルに到達できなかったり、優れている会社がそうでない会社と比べて、スターといわれているプレイヤーが必ずしも多いわけではない(16% vs 14%)といったデータについて言及がなされていました。
それでは「スマートなチーム」とはどのような特徴をもっているのでしょうか。またその特徴をどのような手段で理解したり、解き明かしていくのでしょうか?今回のセッションでは、UCLAのマット・リーバーマン博士がチャレンジしているチームの特徴を解明しようとしている研究に注目が集まりました。
リーバーマン博士は、「ニューラル・シンクロニー(Neural Synchrony)」に着目しています。ニューラル・シンクロニーとは、「私たちの脳が、同じときに同じことを行っている度合い」のことを指します。たとえばある実験では、人同士の脳のシンクロ度合いから、その二人の間に友情が芽生えるかどうかを推測することができるそうです。
リーバーマン博士の研究は、fNIRSという新しい機器・技法を用いて、複数の人が同じ作業や相互のコミュニケーションを行っているときに人々の脳がいかにシンクロするかを測定し、それをチームについての分析に生かそうというものでした。リーバーマン博士の研究は、現時点ではまだ発展段階ですが、将来的には、たとえば「ニューラル・インタビュー」「チーム・シンクロニー」「アセス・カルチャー」などに活用ができるのではないかといった構想を語っていました。
 自身の構想を語るUCLAのマット・リーバーマン博士
自身の構想を語るUCLAのマット・リーバーマン博士
「ニューラル・インタビュー」は、ニューラル・シンクロニーを測定することによって、ある環境・チームの中で、その人がThriver(実力を発揮する者)になり得るか、Non-Thriver(実力を発揮しない者)になり得るかを特定できるようになるかもしれないというアプローチです。これにより採用や配属がもっと効率的になったり、応募者の外見によってバイアスが生まれるのをなくすことができるかもしれないといった未来の可能性が語られました。
また、「チーム・シンクロニー」では、チーム内で活動をしているときのニューラル・シンクロニーを測定することで、良いチームの特徴を把握したり、チームワークに影響を及ぼす要因を脳科学的に特定していこうとする構想が述べられていました。そして、「アセス・カルチャー」では、自社のカルチャーの話を聴いている人の脳のシンクロ度合いを見ることで、カルチャーの浸透度合いなどがわかるかもしれないとのことでした。
このように未来の可能性が語られる一方で、それを受け止める会場のオーディエンスの間でかなりざわつきがあったことも印象に残りました。あくまで推測になりますが、こうした技術を用いて、人やチームの善しあしを脳の観点から予測することが可能になるかもしれないといった世界観に、感覚的に恐れを感じた人も多かったのかもしれません。続くパネル・ディスカッションや会場内のダイアログでは、こうした取り組みへの期待に加えて、「シンクロ度合いのみに着目すると、同じ考えの人ばかり増えて、多様性がなくなり、グループ・シンクになることもあるのではないか」「個人の反応や適性がわかるようになると、データを操作的に扱えるのではないか」といった懸念も話されるなど、多面的に探求が行われていました。
 会場では、実際にfNIRSを使ったデータ収集が行われていた
会場では、実際にfNIRSを使ったデータ収集が行われていた
今後さらなる研究や議論が必要になりますが、脳のシンクロに関する研究であったり、チームメイトの適性の把握であったり、人間同士の相互作用を可視化できるようになることには可能性の広がりも感じられます。現在でも、統計データやビジネス理論が多数世の中を飛び交っていますが、ほとんどの人間は、実際のところ、完全に論理的に動いているわけではないといった観点もあります。そうした状況において、今回のように脳科学の観点から人の動きを考えることは、私たちの視界を広げてくれるかもしれませんし、チームの成長だけではなく、その他の領域への適用もできるかもしれません。今後研究活動が進められるとともに、知見を活用する私たち自身も、こうした分野への理解を深めながら、どのようにデータや洞察を適応していくべきか、考えていきたいと思います。
6.『カルチャーの変革』の肝はコヒーレンス(一貫性)を持つこと
「ディスラプティブな言語」を通して、私たちが使う言葉を変革するということは、つまるところ、それを通して企業のカルチャーを変えていくことにつながるように思います。サミットのクロージング・セッションでは、まさに「カルチャーの変革」がテーマに挙げられ、NLIのハイディ・グラント・ハルバーソン博士、CEOのデイビッド・ロック氏、ジョシュ・デイビス氏、メアリー・スローター氏らが登壇し、探求を深めました。
「カルチャーの変革」をいかに進めるのかを考える上で、セッションでは、「コヒーレンス(Coherence)」というキーワードを取り上げていました。コヒーレンスには、様々な意味・捉え方がありますが、ここでは一貫性、凝集性といった意味合いで使われています。カルチャーの変革について建物の構築をメタファーに考えた場合、本来建物を建てるときには、「なぜ建てるのか?」「どれくらいその建物はもつのか?」「どれくらいの人が使うのか?」「人々がその建物に入りたくなる理由は何か?」「周囲の景色とどのようにフィットするか?」といった視点をもとに、全体の一貫性・整合性を取りながらデザインや施行を進めていきます。しかし、新たなカルチャーを築いていくときに、こうしたコヒーレンスがないがしろにされ、ばらばらなコンセプトの建物が乱立するといったことが起きており、それが働く人々に混乱を招いていると、デイビッド・ロック氏は警鐘を鳴らします。
パネル・ディスカッションの中で、ハイディ・グラント・ハルバーソン博士は、脳科学的な視点からも次のようなコメントをしていました。「ある会社で調査したところ、マネジャーをガイドする17のモデルと173の行動が存在しました。これではコヒーレンスは生み出せません。コヒーレンスな状態を保てると、脳は多くのことを考える余裕ができ、キャパシティも高まります。もし、すべてのものがフィットして創られているのなら、あなたの脳はより多くの情報をホールドすることでき、一度に多くのことをマインドで考えられるのです。」
そして、コヒーレントにカルチャーの変革に取り組んでいる企業の例として、マイクロソフトやヒューレット・パッカードが紹介され、両社が自分たちのミッションやバリュー、リーダーシップ・プリンシプルをシンプルかつ一貫性のあるものにするとともに、メンバーの思考を触発したり、内省を促すものになっていることの重要性が語られていました。
 クロージングの講演を務めるハイディ・グラント・ハルバーソン博士
クロージングの講演を務めるハイディ・グラント・ハルバーソン博士
以上ここまで、6つのテーマにわたってニューロリーダーシップ・サミットで行われていた議論の概要を紹介しながら、ディスラプティブな時代に、私たちが生み出していきたいディスラプティブな言語とはどんなものかを考えてきました。今年のサミットをあらためて振り返ってみると、パフォーマンス・マネジメントやリーダーシップ開発といった大枠のテーマから、より個別的・具体的なテーマへの踏み込みが見受けられ、その中で脳科学のインサイトの適用を促進していこうという動きが感じられました。デイビッド・ロック氏は、変革を進めていく上での3つのキーワードに、「Robust(力強さ)」「Resilient(レジリアント)」「Adaptive(適応的)」を挙げていました。私たちが、人・組織づくりの中で扱う言語をより豊かなものにしながら、ディスラプティブな時代に向き合い、力強く、かつレジリアントに変化に適応していくあり方をぜひ今後も探求していきたいと思います。
